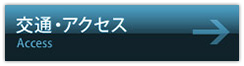借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■借金の相談
■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
|---|
お気軽にお問合せください
亡くなった親の借金の時効と返済義務‐秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
亡くなった親の借金は、時効の援用をすれば、返済義務がなくなります。
■亡くなった親の借金を請求されたときの対処法
・亡くなった親の借金には時効があり、原則最終返済日から5年または10年経過すれば時効になる。
・ただし自動的に時効が成立するわけではなく、時効の援用の手続きが必要。
・時効の援用をするときは、時効援用通知を作成して、内容証明郵便で債権者へ送付する。
・時効が成立すれば、借金の返済義務がなくなる。
・相続人が債務承認すると、時効が中断(更新)され、時効期間がゼロにリセットされる。
・時効の援用をすると、裁判所へ相続放棄の申述をすることはできない。
・時効の援用には期限がないが、裁判所への相続放棄の申述には期限がある。
亡くなった人(親)の借金は、マイナスの相続財産として相続の対象となり、法定相続人(子)に支払う義務がある?
亡くなった人から相続した借金にも消滅時効があるので、最終返済期日から5年経過しているときは時効の援用をすれば払わなくていい?
亡くなった人の相続財産とは、現金や預貯金や不動産のようなプラスの財産だけでなく、借金やローンや未払金のようなマイナスの財産も含まれます。
つまり、亡くなった人(親)の借金やローンや未払金等の支払い義務も法定相続人(子)へ引き継がれるのです。
亡くなった方(親)が借りたまま返済していない借金も、相続財産なので法定相続人(子)に引き継がれて支払う義務があります。
亡くなった親が残した借金は子どもが相続するので子供に支払義務があります。
亡くなった夫が残した借金は妻が相続するので妻に支払義務があります。
子どもがいない兄弟姉妹が死んですでに両親が亡くなっているときは、故人の兄弟姉妹が借金を相続するので支払義務があります。
借金を残したまま人が亡くなったとき、死んだ人(親・夫・兄弟)から借金を相続した法定相続人は原則借金の支払義務がありますが、5年以上放置していれば時効の援用ができることがあります。
時効の援用をすれば消滅時効が成立して、法定相続人は亡くなった人から相続した借金を返済する必要はありません。
親の借金を相続した子供や、夫の借金を相続した妻や、兄弟姉妹の借金を相続した兄弟姉妹は、時効の援用をすれば相続した借金の支払い義務がなくなります。
5年以上借金を放置していても、消滅時効は自動的には成立しないので、相続人が時効の援用をしなければ借金は消滅しません。
債権者と話をすると、債務承認して以後5年間時効の援用ができなくなる恐れがあるので、電話をかけるのは危険です。
時効の援用の手続きは相続人自身ですることもできますが、司法書士や弁護士に依頼すれば間違いありません。
■親が借金をしていて、子供が借金の支払いを請求されたときの対処法
親が生きている時と、親が亡くなった後で、子供が借金を支払う義務があるのかどうか異なるので、対応の仕方も異なります。
1.借金をした親が生きているときの子供の返済義務
借金の返済義務を負うのは、原則、借りた本人だけであり、親子の関係であっても、自分以外の人の借金を支払う義務はありません。
親の借金は、本人が生きている限り、原則、子供が支払う責任はなく肩代わりする義務はありません。
ただし、子供が、親の借金の保証人や連帯保証人になっているときは、債務者本人(親)の代わりに支払う義務があります。
2.借金をした親が亡くなったときの相続人の返済義務
借金を残したまま親が死んだときは、法定相続人は相続した借金を支払う義務があるのでしょうか?
借金は、原則、負の遺産(マイナスの相続財産)として相続人に引き継がれるので、法定相続人は相続した借金を支払う義務があります。
そこで、借金をした親が亡くなった後、相続人(子ども)宛てに、相続した借金の督促状が届いたときは、無視せず対応しましょう。
相続した借金の支払いを請求されたとき、相続人(子供)は、裁判所の相続放棄の手続きや、時効の援用の手続きをすることによって、相続した借金の支払い義務を免れることができます。
自分で対応できないときは、司法書士や弁護士に相談しましょう。
3.死亡した親の借金を請求されたときの時効の援用
親から借金を相続したとき、相続した借金の返済期日から5年経過して時効を迎えていれば、相続人(子供)は、時効の援用の手続きをすることによって返済義務を免れることができます。
➡ 秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
死んだ人から相続した借金の時効の援用を依頼。
借金を相続する人と相続割合
借金を残したまま人が亡くなったとき、借金も相続の対象となりますが、誰が借金を相続するのでしょうか?
故人の借金を相続して支払義務を負う人は、民法が定めている法定相続人です。
借金を相続する割合は、民法が定めている法定相続分のとおりです。
①第1順位の法定相続人→配偶者と子供
配偶者が2分の1,子供が全体で2分の1の割合で相続する。
②第2順位の法定相続人→配偶者と直系尊属(父・母)
配偶者が3分の2,直系尊属が全体で3分の1の割合で相続する。
③第3順位の法定相続人→配偶者と兄弟姉妹
配偶者が4分の3,兄弟姉妹が全体で4分の1の割合で相続する。
■死んだ父親の借金は誰が相続する?相続する割合はどうなる?
父親が借金を残して亡くなったとき、死んだ父親の借金は、法定相続人である配偶者と子どもが相続して、相続した借金の返済義務を負います。
相続する借金の割合は、法定相続分のとおりなので、配偶者が2分の1,子どもが全体で2分の1となります。
たとえば、父親が借金を残して亡くなって、配偶者と子供2人が借金を相続したとします。
その場合は、配偶者が借金の2分の1を相続し、子供2人がそれぞれ借金の4分の1を相続して、借金の返済義務を負います。
死んだ父親が200万円の借金を残したときは、配偶者が借金100万円を相続し、子供2人がそれぞれ借金50万円を相続して、借金の返済義務を負うのです。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
相続した借金を請求されたとき、返済期日から5年経過していれば、時効の援用の手続きを司法書士に依頼しましょう。
親から相続した借金を請求されたとき、債務承認しないで、時効の援用の手続きをすれば、相続した借金の支払義務がなくなります。
相続した借金が時効を迎えているにもかかわらず、相続人が裁判所に訴えられたときは、裁判に対応すれば時効の援用ができることがあります。
秀都司法書士事務所は、時効の援用の成功報酬が無料な事務所です。
司法書士は、借金の元金残高が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。
借金を相続したくないとき
借金を相続したくない時、相続人は、被相続人の死亡を知った時から3カ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をすることができます。
裁判所の相続放棄は「亡くなってから3カ月以内」という期限があるのが注意点です。
家庭裁判所が相続放棄の申述を受理したときは、相続人は、被相続人の借金を相続しなくてすみます。
家庭裁判所への相続放棄の申述は、相続人ごとに手続きをしないといけません。
家庭裁判所へ相続放棄の申述をすると、被相続人の借金を相続しないだけでなく、不動産(土地・家屋)、預貯金、株券など一切の資産を相続することができなくなります。
つまり、家庭裁判所への相続放棄は、被相続人の借金を相続放棄できるのがメリットですが、被相続人のプラスの遺産も相続できなくなるというデメリットがあります。
相続した借金の時効援用と、裁判所の相続放棄を比較すると、次のとおり。
①相続した借金の消滅時効の援用は、裁判所の関与なしで、内容証明郵便によって手続きすることができる。
②相続放棄の手続きは、家庭裁判所で受理されることが必要なので、裁判所の関与なしに手続きすることはできない。
③時効の援用の手続きには、被相続人の死亡を知ってから3カ月以内という期限がない。
④裁判所の相続放棄の手続きは、被相続人の死亡を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申述することが必要である。
⑤相続した借金の時効の援用をするときは、債権者(消費者金融・債権回収会社)ごとに、時効援用の手続きをしなければならない。
⑥相続した借金の時効の援用をしても、相続人は、被相続人の遺産(現金・預貯金・不動産等)の相続権を失わない。
⑦裁判所に相続放棄の手続きをすると、相続人は、被相続人の借金だけでなく、遺産(現金・預貯金・不動産等一切の資産)の相続権を全て失うことになる。
裁判所の相続放棄ができないとき
相続した借金の時効援用の条件
相続した借金の時効援用の必要書類
消費者金融や債権回収会社から亡くなった人宛てに届いた借金の督促状が必要です。
この督促状には、借金の金額、貸付年月日、期限の利益喪失日、判決・支払督促等の日付などが記載されていることがあります。
時効援用の条件を満たしているかを考える上で重要な書類なので、亡くなった人宛てに郵送されて来た督促状をよく読んでみましょう。
亡くなった人から相続した借金の時効の援用は、司法書士や弁護士に相談できます。
司法書士は、借金の元金の金額が1社ごとに140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。
弁護士は、借金の元金の金額が1社ごとに140万円を超えていても、時効の援用の代理人になれます。
亡くなった人から相続した借金の時効援用の手続きをするためには、借金を残した被相続人の戸籍謄本を取得する必要があります。
故人の戸籍謄本は、除籍謄本となっていることもあります。
必要なら個人の住民票除票も取得すると良いでしょう。
相続した借金の時効援用の手続きを依頼する相続人の戸籍謄本や住民票も取得する必要があります。
相続人が2人以上いるときは、相続した借金を法定相続分に従って相続します。
相続人が複数いるときは、それぞれ、時効の援用の通知(内容証明郵便)を作成して債権者に送付する必要があります。
時効の援用の通知は、配達証明付きの内容証明郵便で作成すると、時効の援用をした事実と日付が郵便局により証明されるので利用しましょう。
相続した借金の時効援用ができないで失敗するケース
①被相続人が裁判を起こされたことがあるけれど、相続人が知らなかったとき
②被相続人が債権者に対して債務承認をしたことがあるけれど、相続人が知らなかったとき
債務承認とは、支払い猶予の申出をしたり、借金の一部を支払ったりすることをいいます。
故人が債務承認したことがなく時効の更新(時効の中断)がされていないことも時効の援用の条件となるのです。
このように、借金の時効の援用には条件がありますから、督促状や通知書の記載事項をよく見ましょう。
内容証明郵便で時効援用を通知すると、時効の援用をしたことの証拠となります。
相続人が相続した借金の時効援用をするときは、相続人であることを証明する戸籍謄本を取り寄せて、自分が相続人であることを証明できるようにしましょう。
相続した借金の時効援用の内容証明郵便には、相続人の法定相続分も記載すると良いでしょう。
兄弟姉妹の借金を相続したときの時効の援用
死亡した兄弟姉妹から相続した借金を請求されたとき、相続人は相続放棄や時効の援用の手続きができることがあります。
兄弟姉妹が借金を残して死亡したとき、被相続人に子どもがいないときは、被相続人の両親が借金を相続します。
被相続人の両親が死亡しているときは、被相続人の兄弟姉妹が借金の相続人になります。
兄弟姉妹が借金を返済しないで亡くなったとき、その借金を相続するのは、民法が定めている法定相続人です。
①第1順位の相続人
→亡くなった兄弟姉妹の配偶者と子供
②第2順位の相続人
→亡くなった兄弟姉妹の配偶者と直系尊属(父・母)
③第3順位の相続人
→亡くなった兄弟姉妹の配偶者と兄弟姉妹
兄弟姉妹が亡くなって借金があるとき、第3順位の相続人である兄弟姉妹が借金を相続して、相続した借金の返済義務を負うことがあるのです。
たとえば、一度も結婚せず、独身のまま亡くなった兄弟姉妹がいるときは、被相続人の兄弟姉妹が借金を相続することがあります。
兄弟姉妹が借金を相続したくないときは、被相続人の死亡を知ってから3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理されれば、借金を相続しません。
家庭裁判所に相続放棄の申述をしないで、兄弟姉妹の借金を相続したときは、5年以上借金を放置していて、消滅時効期間が経過しているときは、相続人は消滅時効の援用をすることができます。
ただし、兄弟姉妹の借金について、相続人が支払猶予等の債務承認をすると消滅時効の援用ができなくなってしまいます。
亡くなった親の借金で裁判を起こされたとき
亡くなった親が借金を払っていなかった場合に、相続した子どもが裁判を起こされたときは、裁判を無視できません。
亡くなった親の借金で裁判を起こされたときは、答弁書や異議申立書の作成や訴訟対応を司法書士に相談しましょう。
5年以上支払いをしていない場合は、時効を主張できることがあります。
(1)債権回収会社から、亡くなった親の借金で裁判を起こされたとき
債権回収会社(サービサー)とは、法務大臣の許可を受けて、債権回収を専門にしている会社であり、「簡易裁判所」へ訴訟の申立てをすることが多いです。
・ジャックス債権回収サービス株式会社
・オリンポス債権回収株式会社
・セディナ債権回収株式会社
・セゾン債権回収株式会社
・中央債権回収株式会社
・アイアール債権回収株式会社
・アウロラ債権回収株式会社
・アルファ債権回収株式会社
・エムテーケー(MTK)債権回収株式会社
・エーシーエス(ACS)債権管理回収株式会社
・ニッテレ債権回収株式会社
・札幌債権回収株式会社
・リンク債権回収株式会社
・株式会社ティーアンドエス
・れいわクレジット管理株式会社
(2)法律事務所から、亡くなった親の借金で裁判を起こされたとき
弁護士は、債権者(貸金業者・債権回収会社)からの依頼を受けて、裁判所へ訴訟の提起をしています。
・トラスト弁護士法人(れいわクレジット管理・クレディア)
・弁護士法人コモンズ法律事務所(ジャックス)
・引田法律事務所(日本保証、旧武富士)
・みずなら法律事務所(エムズホールディング、シーエスジー)
・子浩法律事務所
・鈴木康之法律事務所
・駿河台法律事務所
・高橋裕次郎法律事務所
・日本橋さくら法律事務所
(3)当事務所が対応している「簡易裁判所」
亡くなった親の借金で裁判を起こされたとき、秀都司法書士事務所に相談。
■対応している裁判所(例)
(東京都)
・東京簡易裁判所
・東京簡易裁判所墨田庁舎民事7室
・立川簡易裁判所
・八王子簡易裁判所
・町田簡易裁判所
(千葉県)
・千葉簡易裁判所
・市川簡易裁判所
・松戸簡易裁判所
・佐倉簡易裁判所
・館山簡易裁判所
・千葉一宮簡易裁判所
・銚子簡易裁判所
・東金簡易裁判所
・佐原簡易裁判所
・木更津簡易裁判所
・八日市場簡易裁判所
(埼玉県)
・さいたま簡易裁判所
・大宮簡易裁判所
・川口簡易裁判所
・川越簡易裁判所
・越谷簡易裁判所
・本庄簡易裁判所
・所沢簡易裁判所
・飯能簡易裁判所
・秩父簡易裁判所
・久喜簡易裁判所
・熊谷簡易裁判所
(神奈川県)
・横浜簡易裁判所
・神奈川簡易裁判所
・藤沢簡易裁判所
・厚木簡易裁判所
・川崎簡易裁判所
(茨木県)
・水戸簡易裁判所
・下館簡易裁判所
・古河簡易裁判所
・下妻簡易裁判所
・日立簡易裁判所
・取手簡易裁判所
・土浦簡易裁判所
・常陸太田簡易裁判所
(栃木県)
・宇都宮簡易裁判所(アペンタクル、旧ワイド)
・小山簡易裁判所
・足利簡易裁判所
・真岡簡易裁判所
・大田原簡易裁判所
・栃木簡易裁判所
(群馬県)
・前橋簡易裁判所
・伊勢崎簡易裁判所
・高崎簡易裁判所
(福島県)
・福島簡易裁判所
・郡山簡易裁判所
(長野県)
・長野簡易裁判所
・松本簡易裁判所
・上田簡易裁判所
(静岡県)
・静岡簡易裁判所(株式会社クレディア)
・熱海簡易裁判所
・三島簡易裁判所
・沼津簡易裁判所
・掛川簡易裁判所(ダイレクトワン株式会社)
・富士簡易裁判所
・清水簡易裁判所
・下田簡易裁判所
(北海道)
・札幌簡易裁判所(ティーオーエム株式会社)
消滅時効の条件(どのような時に時効の援用ができるのか)
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則最終返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
ただし判決等があるときは確定日から10年経過しないと、時効の援用ができません。
消費者金融やクレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則最終返済日から5年 |
②判決等があるときは確定日から10年 |
■貸金業者の消滅時効の条件
貸金業者の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に判決等を取得されていないことが条件。
債務承認とは、借金の存在を認める行為のことで、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などが該当する。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に判決等を取得されていないことが条件。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
代表プロフィール
当事務所がよく利用する簡易裁判所のご紹介

■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)